ダゲレオタイプ&アンブロタイプ見学会レポート-daguerreotypeandambrotype-
- akatsuki-shabou
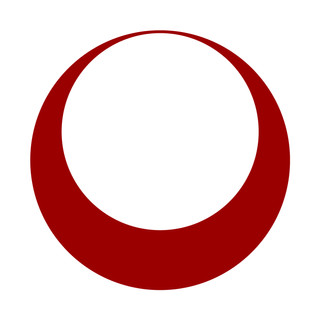
- 2025年8月31日
- 読了時間: 8分
更新日:2025年11月17日
こんにちは本田です。2025年8月24日に開催した「ダゲレオタイプ&アンブロタイプ見学会〜写真のはじまりにふれる1日〜」のイベントレポートです。
このイベントは普及した写真の中で最も古いとされるダゲレオタイプと、その次に発明されたとされるアンブロタイプ(=湿板写真、以下アンブロタイプ)を1日で見ていただけるというものでした。
と言いましても、それぞれ撮影するのにそれなりに時間がかかりますし、使う道具も異なってきますので連続撮影ということにはならず、午前中にダゲレオタイプ、午後からはアンブロタイプというスケジュールです。ご参加いただいたほとんどの方が両方の会をご予約くださり、ダゲレオ&アンブロの特徴をそれぞれに体験してもらう機会となりました。
まずはダゲレオタイプの会からプロセスを交えてレポートしていきます!

ダゲレオタイプ(銀板写真)
1839年にルイ・ジャック・マンデ・ダゲールにより発明された世界初の実用的写真撮影法
あかつき写房でアンブロタイプ以外の写真を紹介するのはコロタイプ以来でしょうか。こうして、講師の方をお迎えしてのイベントは初めての試みでした。
担当してくださるのは、日本屈指のダゲレオタイピストであり日本写真協会会員の名久井伴久さんです。本田が簡単な挨拶をさせていただき、名久井さんにバトンタッチ。ダゲレオタイプの歴史的なお話と書籍の紹介などから始まりました。

ダゲレオタイプは鏡に像が残っています。写真を撮るためにはその鏡を作るところから始めなければなりません。え、鏡を作るって??となっているところに、名久井さんがメッキした銅板を磨くところを実演してくださいました。
トライアルの時に私も実際にやってみましたが、、、傷を消そうと磨くとまた次の傷ができてしまうという状況に陥ってしまい全面傷なく磨くのはかなりのテクニックが必要でした。名久井さんが磨くと数分でピカピカです。机にはメッキ前の銅板、メッキだけ施した銅板、荒く磨いた銅板が並んでいます。
磨いた銀板をドライヤーで温めて、ヨウ素を吸収したシリカゲルの入った木箱にセットします。40秒から60秒くらいで銀板の表面の色が変わります。薄いオレンジになったら感光板の出来上がりです。
感光化した銀板を撮影用のホルダーに詰めたらいざ撮影!
撮影には開発したカメラnew moon を使用しました。今回のために6×6用のホルダーを特注しています。湿板写真専用としていますが、ダゲレオタイプの感光領域と湿板写真の感光領域は似ており、とても相性が良いです。名久井さんにもお墨付きをいただき今回のイベントでも採用となりました。被写体は時計とカラーチャート。バックアップをかねて、二段重ねで撮影しています。絞りf11、露光時間は4分。
撮影したら現像作業です。ダゲレオタイプの現像はいくつか方法があるのですが今回の見学会ではベクレル現像という方法を採用しました。
やり方は、撮影ホルダーにシルクスクリーン用のフィルムをつけて、遮光板を開けて紫外線で約15分再露光するというものです。直視すると目が疲れるのでじっくりと見ていられませんがじわじわと像が現れ始めます。目視で現像時間を確認できるのはいいところですね。
現像が完了したら、最後に定着作業を行います。薬品はチオ硫酸ナトリウムを使います。さっと浸したら、精製水で濯いでブロアーで水滴を飛ばしたら完成です。ちゃんと写っていて一安心。トップ写真を見ていただいたらわかりますが、像が反転していて、時計の針が動いているのがわかります。カラーチャートは少し端が見切れてしまっていますが感光特性がわかって面白いです。名久井さんお疲れ様でした。
さて、後半は私たちが担当します。ブログが長くなるので分けようかと思いましたが、せっかく写真の始まりにふれる1日としていますので、あえてこのまま続けてみようと思います。

アンブロタイプ(湿板写真)
1851年フレデリック・スコット・アーチャーにより発明された写真技法。
※ガラスを支持体とした湿板写真のことをアンブロタイプと呼ぶ、他にもアルミを支持体としたティンタイプなどがある→そのことを書いたブログ
今までもアンブロタイプのやり方はこのブログでも何度か書いておりますが、今回はダゲレオタイプと比較しながら書いてみたいと思います。
まず、アンブロタイプも支持体であるガラスを磨きますが、ダゲレオタイプの表面の傷を消す意味での研磨ではなく、アンブロタイプは表面の油汚れなどを磨き取るという意味です。窓拭き的な感じですね。今回の見学会では磨いたガラスを用意していたので、この工程は割愛しました。

そういえば!気付いた方もいらっしゃるかもしれませんが、ダゲレオタイプは暗室というほど暗い部屋が必要ありません!それは単純に感光剤の感度が低いからということと、部屋の照明にはほとんど感光しないからです。ダゲレオタイプよりも数段感度が高いアンブロタイプは、現代のフィルムプロセスのようなきっちりとした暗室は必要ありませんが、それでも赤い光である必要があります。
技術担当は小椋です。ガラスにコロジオンを塗布して硝酸銀溶液に浸します。溶液の入ったケースなどは全て手作りです。これはダゲレオタイプも同じで、ヨウ素の入った箱などは全て自作です。
約4分後、硝酸銀から出てきたガラスは乳白色に変わっています。これらをホルダーに詰めて撮影します。この時、板は溶液で湿っているのですが、この板が乾くまでに写真を撮影して現像処理までの作業をしてしまわなくてはなりません。湿っている板が湿っている間に撮影するので、「湿板写真」と呼ばれています。一方ダゲレオタイプは鏡に像を写すので「銀板写真」と言われたりもします。
いざ撮影。屋外のガレージに出て集合写真を撮影しました。直前まで雨がパラついていましたが撮影時は日差しが出てきました。被写体は影に入れて、絞りf16、露光時間は8秒でした。名久井さんに聞いたところダゲレオタイプだと、10分から15分くらいの露光が必要とのことでした。人物を撮るという点ではアンブロタイプの方が良さそうです。
使用カメラはnew moon 4×5。撮影したら速やかに暗室に戻ります。

ホルダーからガラスを取り出し、ざっと現像液をかけると20秒ほどでネガ像が現れます。ダゲレオタイプが15分ほどかかるのに対して、アンブロタイプは一瞬で像が出てきます。
現像したガラスを定着液に浸すと、ネガ像がみるみるうちにポジ増へと変化していきます。何度見ても感動する瞬間です。
定着液はチオ硫酸ナトリウム。濃度は違うのですがダゲレオタイプも同じ薬品です。それどころか、この薬品は市販のフィルムや印画紙でも定着液として使われている薬品で、古典写真の薬品としては数少ない量販店で手に入る薬品の一つです。
さて、できた写真は、、、すみません、よくわからない白い物体がたくさん写り込んでしまいました。カメラに直射日光が当たっていたのでフレアでしょうか?いや、フレアってこんな感じに写るかな??と皆で議論しながら、答えは分かりません。撮り直しすることもできましたが、今回はプロセスを見ていただくのがメインでしたので再撮影はしないことにしました。参加者の方からはこの時しか写らないものですよねと言われて救われましたが、、、いやあ、お恥ずかしい、、久しぶりに人前で失敗らしい失敗をしました。

さて、いかがでしたでしょうか。
ダゲレオタイプとアンブロタイプの違いがなんとなくわかっていただけたでしょうか?
正直、Webや書籍でこれらの写真を見ても違いはわかりません。それどころか、ただのモノクロ写真にしか見えません。見て、触れて、体験することで、初めてその違いや趣に気づくことができます。
ダゲレオタイプが発明されてからアンブロタイプができるまでの間は約12年ほど。感度が上がり、コストが下がったことで、一気に写真は普及します。しかしアンブロタイプが開発された後もしばらくは、ダゲレオタイプの方が高級な写真として残っていたんですね。確かに実際に比べてみると、それぞれに良さがあることが分かります。2025年に撮りたてのダゲレオタイプとアンブロタイプを比較することは、果たしてどのくらいの贅沢なのでしょうか。
参加者の皆さまには、自身でやってみるならどっち?撮ってもらうならどっち?などと楽しく雑談と交流を深めることができました。
さあ、長文になりましたが、これを読んでやってみたい、見てみたいと思った方はぜひ、私たちの活動をフォローしてくださいね。来週はいよいよワークショップです(詳細は文末リンクより)。
最後になりましたが、ご参加くださった皆さま、講師の名久井さん、発起人でありトライアルにも参加したいただいた川畑さん、このイベントをシェアしてくださった皆さま、その他関係者の皆さま、本当にありがとうございました。
そして今後ともよろしくお願いいたします。
9月6日、7日にはワークショップを開催します!ダゲレオタイプの会は満席となっていましたが追加日程が決定しました!詳細は以下のページにありますので、ご興味のある方はぜひ覗いていってください!※終了しました
最新のワークショップ情報はこちら
お問い合わせはメールまたはLINEでお願いします
LINE






























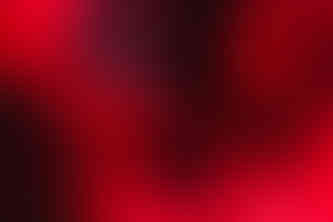














コメント