現代の湿板写真を作るプロジェクト-Shippan Redesign project-
- akatsuki-shabou
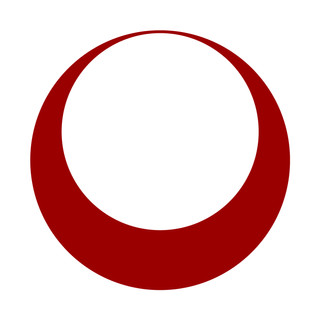
- 2025年10月15日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年11月17日
こんにちは、あかつき写房の本田です。今日は湿板写真関連のプロジェクトをご紹介します。その名も「Shippan Redesign Project」ちょっと読みにくいですね、、、「シッパン リデザイン プロジェクト」と言います。名前からお察しいただける方もいらっしゃるかと思いますが、湿板写真をリデザインしようというプロジェクトです。この記事では、プロジェクトの始まりから、カメラの開発に至った経緯、コンセプト、湿板写真の未来についても書いてみることにします。少し長くなりますがどうぞ見ていってください!それではどうぞ。

湿板写真専用カメラ プロトタイプ1
「原点 - 湿板写真との出会い」
2018年夏に東京の田村写真で湿板写真を習いました。京都に持ち帰り、必要なもののリストを作成しますが、なんせ、すぐに使えるようなものが売っていません!!無いものは作る、代用する、または作ってくれるところや売ってくれるところを探しまわりました。きちんと撮影ができるようになるまで約4ヶ月ほどかかりました。この経験が、後の私たちの活動の出発点となったんです。

Photo by Masami Tamura
「縁 - 技術を守る物語」
私たちは、湿板写真の道具を作るためにfab cafe 京都というところに出入りしていました。そこで出会ったのが現新工芸舎代表の三田地さんでした。三田地さんは3Dプリンタを使って工芸品を作るチャレンジをされています。fab cafe 京都で開催されていたイベントで登壇されている時に、織物業界の話をされていました。はた織りの時に使う「シャトル」という横糸を通す道具を作る職人さんがいなくなることで、織物産業、織物文化自体がなくなってしまいそうだったところ、3Dプリンタを使ってシャトルを作ることで、産業、文化を守ることができたという話でした。私たちがまさに直面していること、道具の調達ができないために湿板写真ができないという現状と重なり、すぐに湿板写真の現状を伝えにいったことを覚えています。
その後、プロジェクトが立ち上がり、三田地さんからカメラや写真についても造詣が深い小坂さんへとバトンタッチ。私たちがnew moon シリーズとして販売しているプロダクトは全て小坂さんのデザインです。
「使命 - 道具と技術の継承」
Shippan Redesign Projectのトップページには「現代の湿板写真をつくる」と掲げています。これはどういうことでしょうか?湿板写真を撮影するだけであれば、ひたすら懐古的に湿板写真を復刻し写真館などをすることもできました。明治の道具を集めて、当時のテキストを読み解いて、当時の作法で写真を作る。これは素晴らしいことです。
しかし、そのような形で復刻できたとしても、私たちが辞めてしまうとその時点で湿板写真の歴史はまた終わってしまうかもしれません。どうせなら、未来に届けたい!その役割を果たしたい!という想いから、まずは現代の湿板写真を作ろう!という考えに至りました。そのために、私たちがやるべきことは二つでした。道具の調達と技術の継承。この二つを叶えるために、カメラの開発と、ワークショップの準備に取りかかりました。
「挑戦 - New moonの誕生」
道具がなければ文化がなくなる!ということで、湿板写真専用カメラの開発をスタート。2020年のことでした。まずは古典カメラを模したものを3Dプリンタで作ってみることから始めました。その後、様々なプロトタイプを経て、現行のnew moon 6×9に辿り着くのですが、実は開発が始まった時はカメラの詳細は定まっていませんでした。試作すればするほどに、フィルム世代のカメラがいかに完成されていたかということが証明されるばかりで、私たちが作るべきものがだんだん分からなくなってきた時期がありました。
そんな中、エンジニアの小坂さんが極限まで機能を削ぎ落としたようなシンプルなカメラを提案してくださいました。これを機に商品化まで一気に漕ぎ着けることができました。シンプルで純粋な、これこそが私たちの目指していた湿板写真のためのカメラでした。

「種蒔き - ワークショップの理念」
ワークショップではカメラを購入し、持ち帰っていただくことにしました。受講者さんには少しご負担になってしまうのですが、世の中に湿板写真のカメラを増やすことで、「道具が手に入らないから湿板写真を諦める」という未来をなくすために、一台でも多くの湿板カメラを作って、たくさんの人に保管してもらおうと考えました。
そのため、new moonシリーズは、初めて湿板写真をされる方に使いやすく、保管しやすく、メンテナンスしやすい作りになっています。ワークショップ後には、撮った写真と一緒にお持ち帰りいただき、できれば目に触れるところに湿板写真と一緒に置いていただくことで、湿板写真に興味を持ってもらえる人が一人でも出てくれば、というところまでをデザインに落とし込んでいます。

「展望 - 湿板写真の未来」
今後湿板写真はどうなっていくのでしょうか。湿板写真を始めて6年目。答えはありませんが、今考えていることを少し書いてみたいと思います。
この6年の間には、コロナ流行のためオンラインコンテンツの充実が加速し、NFTが流行り、AIが登場しました。消費にも創造にもデジタルコンテンツが溢れかえり、そのほとんどはパソコンすら必要とせず、スマートフォン一つで体験することができます。
こんな時代だからこそ、実際に触れることのできるもの、実際に体験できることに価値があると言われます。アナログ回帰です。レコードがCDの需要を上回ったり、フィルム写真をする若者が増えたりという話題を耳にして、少し嬉しい気持ちになるのですが、果たしてこれらに持続性はあるのでしょうか。消費スピードという面においてはただの流行で、デジタルコンテンツと大きな違いが無いように思えます。
ただ、リアル世界に残るという面では廃棄されない限り、またどこかで誰かに見つけてもらえるかもしれないという強みがあります。アナログに爆発的な拡散力はありませんが、長い時間軸で見たときの可能性は大きいと言えそうです。
しかし、この可能性だけにかけてしまうのはちょっと横柄というか危険で、アナログだったらなんでもかんでも良いということではありません。そこにはある程度の普遍的な価値がないといけません。※そもそも普遍的な価値なんかあるの?という議論はいったん横に置いておきます。
普遍的な価値を考えた時に、湿板写真が持つ独特の存在感は無視できません。一枚一枚が唯一無二の作品となり、その過程で作り手の意図と技術、そして偶然性が織りなす魅力があります。私たちが目指しているのは、単なるノスタルジーではなく、現代に生きる表現方法としての湿板写真です。
New Moonシリーズの開発やワークショップを通じて、私たちは「伝える」という役割を担っています。技術を伝え、道具を伝え、そして何より湿板写真という表現手段の可能性を伝えていく。それは決して大きな波とはならないかもしれません。しかし、確実に次の世代へとバトンを確実に渡していくことができる。そう信じています。この魅力を感じ取り、実践していく人が一人また一人と増えていく。それぞれが自分なりの解釈と表現を重ねていく。そうして湿板写真という文化は、より豊かに、より深く育まれていくのだと思います。
ワークショップ情報はこちら
お問い合わせはメールまたはLINEでお願いします
LINE














































コメント